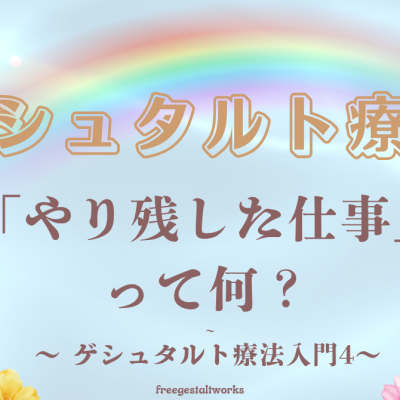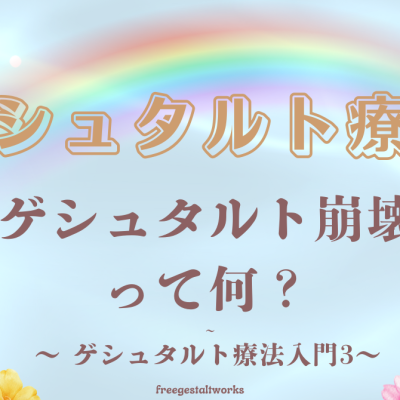- はじめに
- 「ゲシュタルト」とは、形ではない?
- 「全体は部分の総和にあらず」──この名言の意味
- 実生活で感じるゲシュタルト
- なぜ、今「ゲシュタルト」が面白く、かつ、役に立つのか?
- 最後に:見えている世界を、もう一度「見直す」
________________________________________
■はじめに
さて、
「下のものは、何に見えるでしょうか?」
● ●
▲
▽
ひとつひとつを見ると、ただの「丸」と「三角」の並びです。
でも、パッと「ひとまとめ」で見ると、なんとなく「人/キャラクターの顔」に見えてしまいます。
これは、なぜでしょうか?
これがまさに、今回紹介する、
「ゲシュタルト」
ということなのです。
通常、私たちは、このような感覚の中で、世界を見ているのです。
これは、「ゲシュタルト心理学」の考え方です。
________________________________________
「ゲシュタルト(Gestalt)」はドイツ語で、一般には「形」や「全体」と訳されます。
でも、ただの“形”ではありません。
もっと詳しくに言うと、「全体的なまとまりとして知覚される構造/形態」のこと。
たとえば…
・点が3つあれば、「三角形」に見える
・輪郭がなくても、人の顔だと認識する
・音楽のメロディーは、音の羅列以上の“意味”を持つ
このように、人間は、物事を「とらえ」ます。
「部分の足し算(積み上げ)」ではなく、
最初から、「全体としてのまとまり」で物事を把握しようとするのです。
________________________________________
ゲシュタルト心理学を代表する有名な言葉があります。
「The whole is other than the sum of its parts.」
(全体は部分の総和とは異なる)
これは単に「全体=パーツの合計」ではない、という話ではありません。
「全体」は、パーツが集まっただけでは生まれない「別の性質」を持っている、ということを意味しているのです。
つまり、パーツの配置、関係性、脈絡などに、人のとらえ方によって、全体に「意味」が宿るということ。
これは、芸術・デザイン・教育・コミュニケーション理論など、あらゆる分野に応用されています。
________________________________________
■ 実生活で感じるゲシュタルト
このようなゲシュタルトの感覚は、日常でも無意識に体験しています。
▼文章もそうです。
私たちは、単語のひとつひとつの意味を、順に読んでいるだけじゃなく、「全体の文脈」を把握して、私たちは意味をつかんでいます。
また、その文章だけではなく、その文章が、どのような「文脈」の中に存在しているのも感じて、「意味」を理解しています。
▼音楽もそうです。
私たちは、曲を、音やフレーズの寄せ集めではなく、ひとつの生き物のように「全体の構成や形態」を感じて、その曲をひとつの美しさとして聴いています。
音楽のアルバムなども、個々の楽曲の寄せ集めではなく、アルバムとしてのトータルな「別の意味/美しさ/感動」を感じていたりします。
▼人間のチームもそう。
Aさん、Bさん、Cさんが、ただいるだけでは、「チーム」とは言えません。
でも、それぞれの間に関係性が生まれると、ひとつの「チーム」になります。
バンドなどのように、個々人の単なる集まりではなく、ひとつの別の有機的な生き物、「チーム」になります。
________________________________________
私たちは、過剰とも言える、情報過多の時代に生きています。
特に、ネット社会のバラバラな断片的情報があふれる中で、
「どう全体像をとらえるか」
がますます重要になっています。
その際、ゲシュタルト心理学の視点を持てば、対処の仕方も見えてきます。
個々の情報をバラバラと並べて積み上げていっても、
私たちにとって、それは、生きた「意味」になっていきません。
なんとなく消化不良で、欲求不満になります。
むしろ、逆に、心を閉ざしたくなります。
そんな時、すべての情報の全体像を、一挙に理解しようとするのではなく、
小さな、生きたゲシュタルトのレベルで、感覚的に消化できるレベルで、
物事をひとつひとつ把握していくと、しっくりと理解できるのです。
その小さなゲシュタルトを集合させて、
大きなゲシュタルト(全体像)にするのは、そんなに苦労は要らないのです。
そのような、ゲシュタルト感覚のプロセスによって、
「その情報の本質は何か」
といったようなことも、より深く理解できるようになるのです。
________________________________________
世界を「見ること」は、ただ目に入れることではありません。
それは、「意味」を、ゲシュタルト的に感じとる/形づくることです。
ゲシュタルト心理学は、
私たちが世界をどう意味づけしているのか、
その無意識の「見え方」に気づかせてくれます。
次に何かを「見た」とき、
そこにどんな「まとまり」を自分がつくり出しているか、
少し意識してみてください。
世界の見え方が、ほんの少し変わるかもしれません。
【ブックガイド】
変性意識状態(ASC)や意識変容、超越的全体性を含めた、より総合的な方法論については、拙著
『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』
および、
『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
をご覧下さい。
ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著
『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』
をご覧ください。