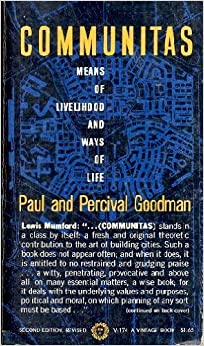
さて、別の「ワークとは」では、ゲシュタルト療法のワークの体験過程について見てみました。
ここでは、ワークの構造とプロセスが、ひろく文化的な文脈(コンテクスト)から見てどのように仕組み(構造)になっているのか、少し普遍的な視点から見ていきたいと思います。
ここで、ひとつ参考になるモデルがあります。
人類学者ファン・へネップがはじめに提唱し、のちに、ヴィクター・ターナーが敷衍した「通過儀礼(イニシエーション)」の過程(プロセス)についてのモデルです。
それによると、例えば、部族社会の「通過儀礼」に参加する若者は、次の3つのプロセスを経て「通過儀礼」を完了していくとされます。
そのことで、社会の成員として受け入れられると言います。
これは、彼ら参加者の内的体験、内的プロセスとして見られるものです。
①分離・離脱(separation)
②周縁・境界(margin/limen)
③再統合・集合(aggregation)
のプロセスです。
儀礼の参加者は、
①まず、構造化された日常生活(日常性)から切り離され、そこから「離脱」します。
②次に、「境界状態(リミナリティ liminality)」にある非構造的(コミュニタス的)な状態に変容していきます。
この状態は、(喩えると)固体のように堅固だった、日常性の構造(文脈/意味)が溶けて、液体のように流動化した状態です。
日常性の構造・文脈(意味)が、相対化(無化)された、曖昧で両義的な状態です。
③再び、構造化された世界に戻ってきます。このことで「再統合」された存在になります。
このようなプロセスを経るというわけです。
イメージで喩えると、蝶の変態のようなものです。
青虫は、成虫の蝶になるために、
①繭をつくりはじめ、青虫の状態から「離脱」します。青虫の状態をやめはじめるのです。
②繭ができるとその中で、青虫の身体は溶けて、液状になりはじめます。流動化された、非構造的な状態になります。「コミュニタス」の状態です。
③流動化した状態から、だんだんと組織化・構造化されて、成虫の羽ある姿に、再構成されます。
そして、繭から出る時は、青虫からまったく別物の姿で現れてくるのです。
実は、このようなプロセスは、ゲシュタルト療法のワーク(セッション)におけるプロセスと大変似通ったものとなっているのです。
ワークの体験過程においては、
①分離・離脱 まず、ワークの体験空間に入るということで、クライアントは、普段のありきたりの日常性から離脱していきます。自らを切り離していきます。
日常的な意識状態から離脱していきます。
②周縁・境界 次にワークが深まり進展していくと、クライアントは感覚的な没入状態から、軽度の変性意識状態に入っていきます。
それは、構造化された日常意識とは違う流動化した状態です。
クライアントの意識状態は、リミナリティとコミュニタスの領域(状態)にあり、それは、意識と無意識との深い交流が起こっている状態です。
③再統合・集合 ワーク終盤では、無意識(潜在意識)からの資源(リソース)を持ち帰りつつ、日常的な自我との再統合をはかっていきます。
以上のように、ワークの体験過程自体が、ある種の通過儀礼的な過程(プロセス/仕組み)を持っているのです。
ところで、V・ターナーは、上記の過渡的状態、境界状態(リミナリティ)に現れる存在状態を、「コミュニタス」と呼びました。
そして、社会におけるコミュニタスの機能を、構造化された日常性や社会に対置した、「流動化した状態」としたわけですが、そのコミュニタスの特性や必要性をさまざまに記しています。
(ちなみに、このコミュニタスという言葉は、パールズと共にゲシュタルト療法を創った作家ポール・グッドマンより来ていると言われています)
「コミュニタスは、実存的な性質のものである。それは、人間の全人格を、他の人間の全人格との関わり合いに、巻き込むものである」
「コミュニタスは、境界性(リミナリティ)において、社会構造の裂け目を通って割り込み、周辺性(マージナリティ)において構造の先端部に入り、劣位性(インフェリオリティ)において構造の下から押し入ってくる。それは、ほとんどいたるところで、聖なるもの、ないし”神聖なるもの”とされている。恐らく、それが構造化され制度化された諸関係を支配する規範を超越し、あるいは解体させるからであり、また、それには未曾有の力の経験がともなうからであろう」(ターナー『儀礼の過程』冨倉光雄訳 新思索社)
ここでは、コミュニタスの力(境界状態 リミナリティ liminalityの状態)が、社会構造を再編する力として、さまざまな社会階層から流入する姿が描かれていますが、これは、心のモデルとしても同様に考えることができるのです。
既存の日常意識の構造に、沸騰した無意識(潜在意識)の力が交錯し、心の構造そのものを刷新・再編するプロセスです。
そして、このことはゲシュタルト療法の深いワークのなかにおいても起こってくるというわけなのです。
ゲシュタルト療法のワークは、一般に「深いワーク」と「浅いワーク」に区分されますが、当然、ここで描いたワークし、「深いワーク」で十全に起こってくることとなります。
最近の巷にあふれている「浅いワーク」では、このようなことは起こらないことも、最後に注意事項として付記しておきたいと思います。
【ブックガイド】
ゲシュタルト療法については、基礎から実践までをまとめた拙著
『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』
をご覧下さい。
この通過儀礼と人格的変容の全体像については拙著をご覧ください↓
『砂絵Ⅰ: 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
