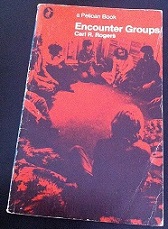
「体験的心理療法」とは、主に1960年代に、米国西海岸を中心に世界へ広まった、新しい心理療法のタイプの一群です。
日本では、体験的心理療法の普及や、満足いく成熟もなかったために、一般的には、イメージのつきにくいものとなっています。それは、同じ1960年代に米国西海岸から世界に広がった「サイケデリック体験」の本質が、日本ではまったく理解されていないことと同様のケースと言えます。
これら体験的心理療法の価値は、今現在、日本の中で気づいている人はほんのわずかしかいませんが、人類の進化的な行き詰まりを打開できる、数少ない方法の一つなのです。
さて、体験的心理療法とは、クライアントが「実際に何か体験すること」を、方法論の中心においた心理療法です。
通常、日本で、「カウンセリング」「セラピー」と言ったら、椅子に座って、セラピストとクライアントとが何かお話ししているだけというものだと思います。
しかし、体験的心理療法の多くは、そういう静的なものではなく、セラピストの提案に基づく「或る体験的なことを行なうことで」クライアントの方が変容していくセラピーとなっています。
見た目にも、椅子から離れて動く、動的(ダイナミック)なものが多くなっています。
当スペースの主たる技法である「ゲシュタルト療法」、「カウンセリング」の創始者で有名なカール・ロジャーズが晩年に熱中したグループ・セラピーの「エンカウンター・グループ」、肉体に直接働きかけて、肉体の奥底から心や感情を解放していく「ライヒアン(ボディワーク)・セラピー」、呼吸を使って、深い心身の解放を実現する「ブリージング・セラピー」などがその代表的なセラピーとなっています。
日本では、体験的心理療法の一般的な認知度が低く、実践している人々もわずかにはいますが、全体としては、かなりマイナーな部類になっています。
日本においては、1970年代に、個々の流派が個々に輸入され、こじんまりと広まりました。
また、文献的には、1980年代に、それら個々のセラピーを、セラピー全体の文脈の中で位置づける形で、アメリカ帰りの吉福伸逸氏が日本に紹介しました。「トランスパーソナル心理学」の前提にあるさまざまな心理療法として紹介したのです。もっとも、吉福氏自身の実践は、トランスパーソナル的というよりも、体験的心理療法的なのです。
【関連】
→吉福伸逸『トランスパーソナル・セラピー入門』(平河出版社)
→ケン・ウィルバー『意識のスペクトル』(春秋社)
→ケン・ウィルバー『無境界』(平河出版社)
→ケン・ウィルバー『インテグラル心理学』(日本能率協会マネジメントセンター)
また、1960年代当時の普及のメッカとしては、アメリカのエサレン研究所 Esalen Institute などがよく知られています。
ここから、体験的心理療法が、一般に広まったとされています。
エサレン研究所は、いわばワークショップ・センターであり、医療的な機関ではありません。また、学術的な機関でもありません。
しかし、そのために、当時のさまざまな先進的・前衛的な人々が、自由に交流できる場となり、「新しい思想」と「実践的なメソッド」が、坩堝のようにグツグツと煮られ、醸成される空間となったのでした。
そして、この「実践的なメソッド」という点が、一番重要な点なのです。
いくら高邁で、理想な理論が語られたとしても、おしゃべりするだけなら、誰にでもできます。
人間の精神や存在が、その状態に到達する具体的な実践法があり、実際に到達できなければ、何の意味もないからです。机上の空論や、砂上の楼閣でしかないからです。
→アンダーソン『エスリンとアメリカの覚醒―人間の可能性への挑戦』(誠信書房)
(ここで生まれた『エサレン・マッサージ』などは、日本でもここ十数年、急速にひろまってきました)
このエサレン研究所について、トランスパーソナル心理学のスタニスラフ・グロフ博士などは、「人間ラボラトリー」「潜在能力センター」であり、「どの研究機関や大学よりも、心理学と精神医学に貢献してきた」と下の興味深いインタヴュー動画の中で語っています。
※スタニスラフ・グロフ博士のインタビュー ↓ (LSDによるサイケデリック体験ほか)
http://hive.ntticc.or.jp/contents/interview/grof
ここに長期滞在した有名な人では、思想家のグレゴリー・ベイトソンや、ゲシュタルト療法のフリッツ・パールズ、エンカウンター・グループのウィル・シュッツらがいます。彼らは、そこで、さまざまなワークショップを
長期居住者となり、さまざまなワークショップを行ないました。滞在したジョン・C・リリーは、当時のエサレンのワークショップの風景を生き生きと描写しています。
→ジョン・C・リリー『意識(サイクロン)の中心』(平河出版社)
ところで、エサレン研究所をつくった所長のマイケル・マーフィーは、その活動初期に、「エンカウンター・グループ」を実際に体験し、「サイケデリック物質と同じくらい、人を恍惚とさせるものだ」と感想を持っています。
そして、これを、
「新しい、アメリカのヨガであり、個人と宇宙とを結合する道だ」
(アンダーソン『エスリンとアメリカの覚醒』 伊東博訳 誠信書房)
と考えたのでした。「新しい体験的心理療法」についての、当時の人々の位置づけがよくわかるエピソードです。「精神解放」のための新しい方法論だったのです。そして実際に、そのような「心の解放メソッド」や「自己成長のメソッド」として体験的心理療法は一般的に受けとられていったということです。治療的なセラピーという面だけではなかったのです。
そして、実際、このエサレンから、体験的心理療法の新しい実践的潮流も、世界へとひろまっていったのでした。
「私は、以前より、開かれ自発的になりました。自分自身をいっそう自由に表明します。私は、より同情的、共感的で、忍耐強くなったようです。自信が強くなりました。私独自の方向で、宗教的になったと言えます。私は、家族・友人・同僚と、より誠実な関係になり、好き嫌いや真実の気持ちを、よりあからさまに表明します。自分の無知を認めやすくなりました。私は以前よりずっと快活です。また、他人を援助したいと強く思います」(ロジャーズ『エンカウンター・グループ』畠瀬稔他訳/創元社)
これは、エンカウンター・グループ体験者の言葉です。
このような心のしなやかさや感度の獲得は、どのような体験的心理療法をやったとしても、それが充分に心身一元論的に深められた場合には、おおよそ共通している要素ともいえます。
さて、では、「体験的心理療法」の特徴とはなんでしょうか?
従来の心理療法と、何が違うのでしょうか?
そもそも、普通の心理療法(セラピー)のセッションは、形の上では、クライアントの方がセラピストに会って「お話しをする」だけのものです。
「お話し」をする過程で、クライアントの方が「自分の話を聞いてもらったり」「さまざまな事柄に気づいたり」「自分自身を受け入れていく」プロセスを通じて、癒されていくというタイプのものです。
現在でも、多くの心理療法(セラピー)はこのタイプのものです。
体験的心理療法を創りひろめた人々(ヴィルヘルム・ライヒ、フリッツ・パールズ等)は、そのようなアプローチでは、人は十分に癒されたり、解放されたり、統合 integrationされたりしないと考えたのでした。
実際、そのような心理療法(セラピー)で、本当に人が奥深く癒される、根っこから解放されるということはありません。
そのため、現在でも、多くの人々は、セラピーやカウンセリングを受けても、多少楽になったが、「根っこにある苦痛」を取り除くという地点には到達することができないのです。
厚生労働省調べでは、日本において、毎年約10万人ずつ精神疾患にかかる人が増えていますが、「増えつづけている」ということは、全体の数から見ると、「治っていかない」ということを意味しているのです。
体験的心理療法を開発した多くの人々は、病や苦痛の根源を、「心身」の深い領域にあると考えていました。
そして、それらは、「思考」や「言葉」のような、表面的な媒体では届かないところにあると直観したのでした。
心身を深いレベルから解放し、治癒するためには、頭で考えたり解釈することではなく(それらはむしろ邪魔・妨害になる)、重要なことは、感情(情動)を肉体的に放出し、表出し、解放することだと考えたのでした。
そして、その感情(情動)は、とりわけ肉体の奥に抑圧されていると見抜いたのでした。
体験的心理療法が、心と肉体を一体のものとしてとらえる「心身一元論的見方」をしているのもそのせいです。
そのため、クライアントの方に「さまざまな感情を直接的に体験してもらう」ことにより、より深いレベルからの癒しと統合、解放が進むことを(具体的技法としたのでした。
「思考を離れ、感覚になれ」という、ゲシュタルト療法のフリッツ・パールズの言葉は、そのことを表しています。
たとえば、ゲシュタルト療法やエンカウンター・グループにおいては、自分の内奥で起きている感情に気づき、実際に他者に表現していくことで、深い感情が解放されるという事態が起こってきます。それがとても深い癒しを生むということを原理としています。
ボディワーク・セラピーやブリージング(呼吸法)・セラピーにおいては、人間は、感情を肉体の底深くに抑圧していて、硬化してしまっているという洞察があります。そのため、クライアントの肉体に直接働きかけ、そこから深い生理的感情を活性化させ解放することで、大きな治癒効果を実現するのです。
これらの方法論は、おしゃべりだけしている表面的なセラピーよりも、効き方も強く大きなもの(強度の癒し体験)となっているのです。
「頭で考える」ことに過度な価値を置き、知的なフィルターのせいで身体(生命)から解離し、袋小路に陥っている現代人にとっては、ダイナミックに心身の弛緩と解放を起こし、生命力と自然治癒力を活性化させ、心身をパワフルに甦えらせる目覚ましい方法論となっているのです。
ところで、体験的心理療法は、心身一元論的な深い領域から解放を促進するため、エネルギーの流動化もとても大きいなものとなります。
それは、「意識」に直接影響する度合いも、とても大きいのです。
というのも、私たちの「意識=日常意識」というものは、肉体の硬直に強く依存・拘束されているものだからです(それが、心身一元論的な本質です)。
そのため、体験的心理療法は、変性意識状態(ASC)を起しやすいという特徴もあるのです。
サイケデリック(LSD)セラピーを行なっていたスタニスラフ・グロフ博士が、LSDの代替物として、ブリージング・セラピーに移行したのも、そのような必然的な流れだったのです。
そのため、変性意識状態(ASC)へのアクセスにおいても、体験的心理療法は、実に有効な方法論となっているのです。
当スペースでは、ゲシュタルト療法の周辺にあるさまざまな体験的心理療法の技法や洞察を活かして、心身の治癒や解放も、意識や潜在能力の開発に役立てているのです。
【関連】
心身一元論的・ボディワーク的アプローチ
ブリージング・セラピー その1 呼吸法と事例
ブリージング・セラピー その2 BPM (Basic Perinatal Matrix)
【ブックガイド】
意識変容、変性意識状態(ASC)を含むより総合的な方法論については、
拙著
『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』
および、
『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
をご覧下さい。
