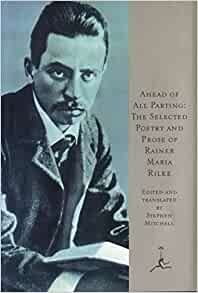
◆天使・チベット仏教・ベイトソン
さて、以前、映画『攻殻機動隊』に出てくる「さらなる上部構造にシフトする」という言葉をめぐって、グレゴリー・ベイトソンの学習理論などを参照し、さまざまにイメージを拡げて考察を行なってみました。
→映画『攻殻機動隊』ゴーストGhostの変性意識
→「聖霊」の階層、あるいはメタ・プログラマー ジョン・C・リリーの考察から
そして、その中で、私たちの日常意識が「上部構造にシフトする」かのような状態を仮定して、その中で起こるかもしれないシステム的な情報の流れ(整列)や、体験内容などについても考えてみました。
また、それらが、下位構造としての私たちの日常意識の情報を書き換えてしまう可能性についても考えてみました(それが癒しや変容の体験になったりするということです)。
今回は、その部分について、もう少し見ていきたいと思います。
特に、普段の日常生活の中で、そのような上位階層のシステムを予感させる何かを垣間見たり、また、その影響を受けたりすることがあるのだろうかというような事柄についてです。
そのような機会を考えてみると、それらは多かれ少なかれ、変性意識状態(ASC)の要素を持っているものですが、散発的には、存在していると思われるのです。
◆〈美〉的体験の通路
例えば、ある種の美的な体験などが、それに当たります。
しかしながら、この場合の美とは、単なる表面的なキレイさではなく、心と体験の奥底に入り込み(侵入し)、そこで振動を拡大させていくような種類の、深遠な〈美〉的体験です。
そのような〈美〉的体験は、私たちが通常、あくせく働いている凡俗の日常的現実に回収され尽くさない〈何か〉の要素があります。芸術が、すべてのものではないですが、私たちを誘引する要因のひとつです。
それらの〈美〉は、日常生活とは違う次元の、普遍的な秩序を感じさせたりもするのです。
変性意識状態(ASC)的で、奥行きと拡がりをもった宇宙的な秩序を予感させるものでもあるのです。
それらは、知覚力の拡大感、恍惚感、覚醒感、本物の実在感といった、あたかも「より上位の階層から」の情報の侵入を印象づけるようなものでもあるのです。
たとえば、壮大な自然の〈美〉などは、そのようなことを感じさせる普遍的な事例のひとつです。山脈のつらなる雄大な峰々の風景や、水平線に沈むこむ巨大な夕日の風景などは、永遠にも似たその圧倒的な〈美〉の情報を処理しきれないために、私たちを胸苦しくさせます。私たちを圧倒する、崇高で耐え難いまでの美しさです。
それらは、巨大な自然界のもつ、高次の階層秩序による莫大な情報量が、 私たちの凡俗の日常意識の許容量では処理しきれないほどに、大量に殺到して来るためであると、論理づけることもできるのです。
◆怖るべき天使とバルドゥ(中有)の如来
さて、世界の歴史的な事例を多く見ていくと、〈美〉に関する、そのような事態が、日常意識を圧倒するような形で、個人を襲う可能性も想定されるのです。
たとえば、ドイツの詩人リルケは、その『ドゥイノの悲歌』の冒頭近くで、歌っています。
「よし天使の列序につらなるひとりが不意にわたしを抱きしめることがあろうとも、わたしはそのより烈しい存在に焼かれてほろびるであろう。
なぜなら美は怖るべきものの始めにほかならぬのだから」
「すべての天使はおろそしい」
(手塚富雄訳『ドゥイノの悲歌』岩波文庫)
彼は、ドゥイノの海岸での或る体験によって、この詩を書きはじめたのです。
そして、彼は、自作の翻訳者フレヴィチに宛てた手紙の中で、この詩について大変興味深いことを述べているのです。
「悲歌においては、生の肯定と死の肯定とが一つのものとなって表示されております。その一方のもののみを他方のものなしに認めることは、我々がいま此処でそれを明らかにするように、すべての無限なるものを遂に閉め出してしまうような限界を設けることであります。死は、我々の方を向いておらず、またそれを我々が照らしておらぬ生の一面であります。かかる二つの区切られていない領域の中に住まっていて、その両方のものから限りなく養われている我々の実存を、我々はもっとはっきりと認識するように努力しなければなりません。
……人生の本当の姿はその二つの領域に相亙っており、又、もっと大きく循環する血はその両方を流れているのです。そこには、こちら側もなければ、あちら側もない。ただ、その中に『天使たち』―我々を凌駕するものたち―の住まっている、大きな統一があるばかりなのです」(堀辰雄訳 青空文庫)
ここで語られている体験領域が、単なる内部表象のひとつだとしても、日常意識のものではない(それでは処理しきれない)、ある種の圧倒的な変性意識的な世界だとは類推できるでしょう。
それは、生と死をひとつと見なすような、(当然、私たちの日常意識はそれらを別々に見なしているわけですが)無限なる体験領域なのです。
また、論理的に考えると、その体験領域は、私たちの日常意識を、その下位の一部とするような、上位階層の世界だと類推することができるのです(「天使」云々をいうのですから)。
そして、また、このような階層(体験領域)の侵入といった「怖るべき」圧倒的な事態がリルケに限らず、世界の諸々の変性意識の事例を見ても、さまざまに起こっていることが、分かるのです。
例えば、以前、『チベットの死者の書』について、その心理学的な見方について検討しました。
→心理学的に見た「チベットの死者の書」
死者の書の中では、移り変わっていく死後の空間、各バルドゥ(中有)において必ず二つのタイプの如来たちが、姿を現して来ることが描かれています。
ひとつは、怖れを感じさせるような眩しいばかりの如来と、もうひとつは、より光量の少ない親しみを感じさせる如来です。
そして、『チベットの死者の書』のメッセージは、前者の怖るべき如来こそを、自己の本性と見なせというものです。
そうすれば、輪廻から解脱できるだろうというものです。そして、後者の親しみを感じさせる如来に近づいていくと、輪廻の中に再生してしまうというわけなのです。
この現象なども、(ベイトソンの)学習の階層構造に照らして考えると納得的に理解することができます。
怖るべき如来は、上位階層からの過剰な情報であるため、私たちには、怖るべきものに感じられてしまうのですが、その「上部構造にシフトする」ことで、無我と解脱が得られるというわけです。
一方、親しみを感じさせる如来は、慣れ親しんだ二次学習であるがゆえに、自我と再生の道に進んでしまうというわけなのです。
つまり、どちらの如来に、コンタクト(接触)するかで、上部階層へシフトできるか、それとも下位階層に留まる(ダブルバインド)かの選択になっているというわけです。
さて、ところで、筆者自身、拙著『砂絵Ⅰ』の中で、さまざまな変性意識状態(ASC)の体験事例について記しましたが、それらの中でも強度なタイプのものは、どこかに畏怖の念を呼び起こすような光彩をもっていたのでした(また、実際、困難な体験でもありました)ひょっとすると、それらなどもどこかに、上位階層からの情報という要素を持っていたからなのかもしれません。
→拙著『砂絵Ⅰ: 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
【ブックガイド】
気づきや統合、変性意識状態(ASC)へのより総合的な方法論は拙著↓
入門ガイド
『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』
および、
『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
をご覧下さい。
