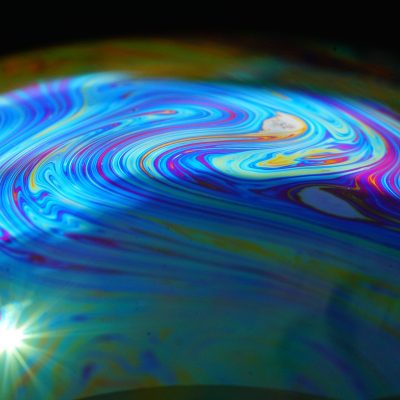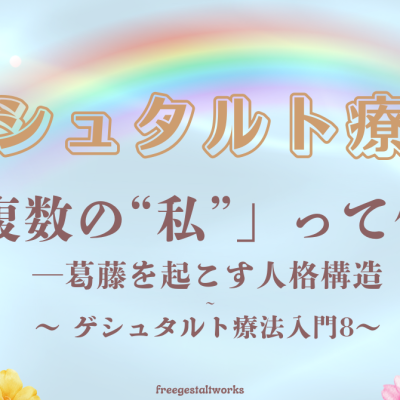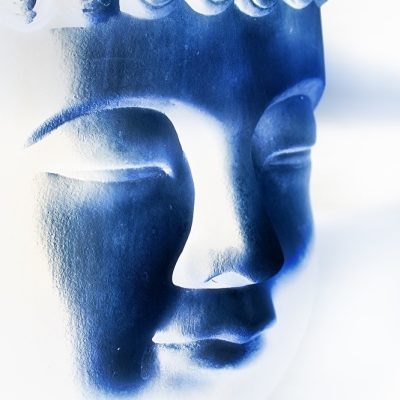私たちは日々、多くの感情を抱えて生きています。
嬉しさ、悲しさ、怒り、不安……。
でも、すべての感情をそのまま素直に受け入れて、感じているかというと、基本的には、そうではありません。
「怒るのは良くない」
「悲しむのは、弱い証拠だ」
「感情的なことは、幼稚で恥ずかしい」
「不快な感情は感じたくない」
「明るくポジティブでいるのが良い」
そんなふうにジャッジして、感情を否定したり、操作するふるまい(パターン)が、知らず知らずのうちに私たちの中に根を張っています。
それが、現代社会の価値観だからです。
その結果、自分の感情に気づかないように、見ないようにするクセがついてしまっているのです。
また、心理学的には、感情を感じないようにするのが、「自我(エゴ)」の機能でもあるからです。
■ 感情を「避ける」ことがもたらす問題
ゲシュタルト療法では、〈気づき〉の力を重視する点を、この入門シリーズで解説してきましたが、特に重要なのが、「自分の感情に気づく」ということです。
というのも、「自分の感情に気づかないようにする」ことが、多くの場合、苦しみや病気の原因だからです。
・怒っているのに「怒ってないよ」と笑ってごまかす
・悲しみを感じているのに、「そんなの気にしてない」と自分に言い聞かせる
・不安なのに、過剰に仕事に没頭して感じないようにする
こうした行動は、世間ではよく見られる行動パターンと言えますが、実は、「自分の心の一部」を切り捨てている(disown)行為でもあります。
そのため、このように感情を抑え込むことを続けていると、その底にある、自分の本当の思いに、だんだんと気づけなくなってしまうのです。
そして、切り捨てられ、抑え込まれた感情は、心の底で、「黒いエネルギー」になって、私たちを脅かすようになるのです。
やがてそれは、心の不調、人間関係のトラブル、そして「なんとなく苦しい」という漠然とした生きづらさへとつながっていくことになるのです。
■ 避けている感情に「気づく」ことの力
では、なぜゲシュタルト療法では「気づき」が大切にされるのでしょうか?
それは、気づいた瞬間に、感情が生き生きと流れ、分裂(抑圧)から統合への変化がはじまるからです。
怒りを感じたことに気づく。
自分が今、寂しいんだと知る。
嫉妬している自分を「ダメ」と否定せず、ただ認める。
こうした気づきは、「自分自身との再会」です。
抑えていた感情に触れることで、心が少しずつ甦っていきます。
そして何より、「今ここ」にある感情をしっかり味わうことは、生きている実感にもつながっていきます。
■ 感情に気づくための小さな練習
避けるクセがついている人が、いきなり「感情と向き合いましょう」と言われても難しいものです。
まずは、小さな練習からはじめてみましょう。
・「今、自分は何を感じてる?」と、しばしば立ちどまって、問いかけてみる
・言葉にならない感情を、色や温度、形でイメージして、表現してみる
・怒りや悲しみが湧いたら、すぐに対処しようとせず、そのままの感情を抱えて味わってみる
このようなアプローチを通して、「気づく感覚」を育てていくことができます。
ゲシュタルト療法では、気づきは、変化のはじまりとされます。
何かを「変えよう」とする前に、まず「気づく」ことが第一歩なのです。
■ 感じることを、自分に許そう
感情を避けてしまう習慣は、そもそも、自分を守るためだったはずです。
でも、もう必要ないかもしれません。
悲しんでもいい。
怒ってもいい。
不安になっても、自分を責めなくていい。
感情は「問題」ではなく、人生を感じるセンサーであり、エネルギーです。
それを避けずに味わうことが、より自由で、より自分らしい力や生き方につながっていくのです。
そう、ゲシュタルト療法は教えてくれるのです。
■おわりに
子どもの頃は、感情を避けることは、生きるための知恵だったかもしれません。
でも、そうすることが、今も必要かどうかは、自分自身で決めていい。
そして、今この瞬間に「気づくこと」から、人生はまた新たに動きはじめます。
【ブックガイド】
変性意識状態(ASC)や意識変容、超越的全体性を含めた、より総合的な方法論については、拙著
『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』
および、
『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
をご覧下さい。
ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著
『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』
をご覧ください。