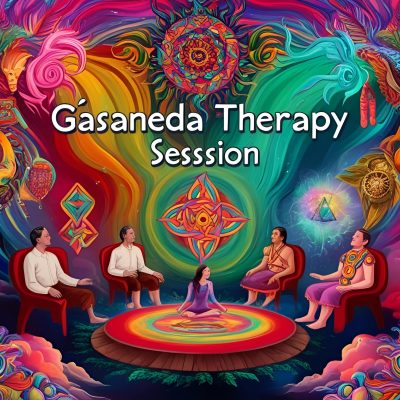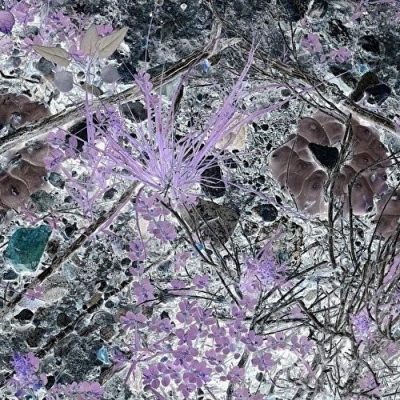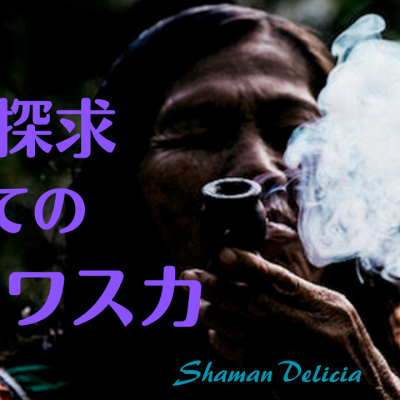最近、現代思潮新社が、9月末で廃業というニュースを聞きました。
現代思潮社といえば、ジョルジュ・バタイユの『内的体験』や『有罪者』、モーリス・ブランショの『文学空間』『来るべき書物』など、特別な本を出していた出版社でした。以前、記事でもとりあげたノヴァーリスの『日記・花粉』を含んだ古典文庫などのシリーズもありました。他にも重要な作品が色々とあります。
→「混乱は、力と能力の過剰を意味する」―ノヴァーリス
ブランショの『文学空間 L’espace littéraire 』は、真に読むに足る、数少ない、並外れた書物のひとつですが、そのような本がもう刊行されていないというのも、出版だけに限らず、精神のレベル全般において、この国の末世(終焉)をよく伝えているようです。
個人的な思い出でいえば、高校時代に初めて神田の古本屋街に行ったときに買った本が、当社の(昔企画倒れになった)『アントナン・アルトー全集』(※1)の第一巻であったというのも、何か妙な「縁」を感じさせるものです。当時たいしてアルトーのことなど知らなかったはずなのに、何か直観があったのでしょう、今思い返しても、色々と暗示的です。このような、作品とのめぐり合わせには、いつも不思議な「縁(布置/コンステレーション)」を感じさせられるものがあります(※2)。
そんなことを考えているうちに、ふと、昔あった「牧神社」のことを思い出したのです。
今では、ネットで検索すると、AIに、「牧神社という名前の出版社はありません」と、答えられてしまいますが、かつて、牧神社という出版社はあったのです。
私自身、知ったときはすでに倒産していた会社でしたが、古書店にそれらの本を見かけて、強い印象をもったのです。
牧神社は、思潮社にいた人が起こした会社で(もう亡くなられていると思いますが)、本人の回想録を読んでも、季刊誌『牧神』は、思潮社の季刊誌『思潮』(1970年頃のもの)を継いだ様子がうかがえます。
当時の『思潮』も、シュルレアリスム(超現実主義)やその周辺のものがとりあげられ、最終号は、『ネルヴァルと神秘主義』であり、アルトーの素晴らしいネルヴァル論(?)が収録されていました。思潮社からも、当時、ミシェル・レリスの作品集や哲学者ガストン・バシュラールの著作など、印象深いものが多く出されていました。
季刊誌『牧神』も、ゴシック・ロマンスや幻想文学、ノヴァーリス、ウィリアム・ブレイク、神秘主義などがとりあげられ、独特な雰囲気を湛えていました。
出版物も、『ノヴァーリス全集』や『アーサー・マッケン作品集成』、『ロルカ全集』や『ノディエ選集』、ヤーコブ・ベーメの『黎明』やジュール・モヌロ『超現実と聖なるもの』など、不思議な香りをもったものが出されていました。昔は、『ノヴァーリス全集』など物も少なかったのか、高いプレミアがついていて、とても手に入るものではありませんでした(一時の「サンリオSF文庫」みたいなものです)。
社名の由来は見たことないのですが、作品集も出しているので、おそらく、魔術師アレイスター・クロウリーも絶賛した『パン(牧神)の大神』(アーサー・マッケン)あたりから来たのでしょうか。本の装丁も、美的で印象的だったので、そのような意味でも、妖しげで濃密なけはいがあったのでした。
取引会社が不渡りを出したようで、6年しか営業しなかったようですが、その間に印象深い作品を残したのでした。
私自身といえば、若い時分、「幻視の鉱脈」を発掘する中で、このようなさまざまな書物に親しんだのですが、だんだんと、本を読んでいるという行為自体に飽き足らなくなっていったのでした。
そのあたりの経緯は、別の記事「哲学や思想の凋落 生と存在を変えない思想」でも少し書きました。
→「哲学や思想の凋落 生と存在を変えない思想」
読書とは、結局のところ、「心理的投影 projection 」による代替的満足なので、本を読んでいたところで、自分の「幻視力/透視力」は一向に上がらないし、存在が実際に変容するわけでもないのです。そのような欲求不満が強くなっていったのです。
そのため、もっと直接的に、自分に「幻視/透視/変性意識状態」をつくり出し、自己の存在変容や、自分の能力が拡張/覚醒する実践的方法論にのめり込むことになっていったのです。
その旅路の果てや往還は、拙著『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』にまとめました。その探求は、私自身を、途方もない、想像を絶する宇宙の彼方へと運んで行ったのです。
→『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
ただ、このような旅の経緯や往還を、今振り返ってみると、最初の「召命 calling 」の重要性にも気がつくのです。
私たちが、精神探求の旅に出るには、神話的にも、人類学的にも、重要なきっかけとなる事象の類型(召命 calling)が知られているものです。
人は、「何かの呼び声を聞いて、旅に出る」ことになるのです。
→英雄の旅 (ヒーローズ・ジャーニー) とは何か
→伝統的なシャーマニズムと心理学的シャーマニズムについて
そのようなことに想いをめぐらせると、上で触れたような、昔、世間の片隅にあった暗流、優れた幻視的作品、美的作品の重要性にも気づかされるのです。
例えば、現在の日本のように、ニセモノしかなくなって、それらに埋め尽くされている惨状を見ると、その意味合いもよくわかります。
このような環境(ゴミの山)の中で、年若い人間が、然るべき「鉱脈」を見つけるのも、なかなか至難の業となっているからです。
そして、真理の「鉱脈」、真に〈詩的〉な高み、真の〈美〉が、まったく見当たらないとなると、間接的にでも役立っていた「魂の投影先/受け皿」が何もないので、探求のきっかけ(召命 calling)になる啓示さえ、得られないという始末になってしまうのです。
実際、歴史的にも、真に優れた、天才的な作品は、「魂の投影先/受け皿」として、私たちの魂自身に、〈啓示〉の光を照り返すものであったからです。
そのことで付言すると、元型的であると同時に、尖鋭であるような、優れた幻視的作品を、(オワコンである芸術ゲームなどではなく)まったく別様に再利用することで、真の機能を甦らすことも可能なのです。そのような方向性については、別の記事でも少し触れました。
→透視と決壊―A.ランボーとサイケデリック(意識拡張)体験
→ある未来の意識―ロートレアモン伯爵と変性意識状態
つまりは、それらの中核的な幻視を、未来の「幻視的シャーマニズム」へと向け変える方向性です。
そのような実践的方法論については、上の拙著で、「夢見の技法」として色々と検討してみました。
さて、いずれにせよ、私たちが目覚める/覚醒する体験は、さまざまな場面で存在していますが、特に若い時分においては、意外と、その出遭いの場も限られています。
しかし、その中で、〈美〉的な体験は、もっとも身近なもののひとつです。
たった一曲の音楽を聴くことで、一冊の本を読むことで、〈啓示〉を受け、召命 callingが起こり、人生が変わっていくことにもなるのです。
〈美〉的なものには、当然、薄っぺらいニセモノもあれば、真に〈詩的〉な尖鋭さ、芳香、高みを持ったものも存在しています。そして、後者は、圧倒的に少ないものです。
しかし、真正に〈美〉的なものは、その背後に、ある種の硬質な普遍性、「元型的」なけはいを持っていたりします。
そのようなものに触れたとき、人は、眠りを覚まされたように、真正さにうたれ、(現代文明が吹聴するように)物事の価値はフラットなのではなく、あきらかに〈超越的〉なものが存在することを直観することになるのです。
そのため、探求の初期の段階で、本物の〈美〉的体験を持つということは、とても重要なことでもあるのです。
その結果として、私たちに、魂の全体性(超越的全体性)が啓示され、その後の旅が、予感されることにもなるからです。
→アヤワスカ体験のトータリティ(超越的全体性)―その至高の体験宇宙
そのような感慨とともに、かつて若い時分に触れた、出版物をいろいろと思い出したのです。
(※1)詩人の入澤康夫は、「昔、アルトーのワケのわからないものを翻訳させられた」と語っていましたが、たしかに、当時の刊行予定(第8巻)を見ると、そこには『ヘリオガバルス』と併録の『存在の新しい啓示』 に入澤訳とあります。第一巻以外にも、いくらか翻訳作業が進められていたのでしょうか。
(※2)最近、ティモシー・リアリーの『チベットの死者の書: サイケデリックバージョン』(菅靖彦訳)について、色々な場面で使用したり、言及したりする機会が多くあります。しかし思い返してみると、(高いプレミアがついている)本書も、自分で買ったわけではなく、知り合った出版社の人に、見本品として貰った一冊でした。それを、将来こんなに使い倒すはめになるとは、当時、夢にも思わなかったわけなのです。
→心理学的に見た「チベットの死者の書」―T.リアリ―の取り組み
(※3)「精神世界/スピリチュアル」というジャンルで、書店に棚ができはじめたのは、おそらく1990年代の中頃からですが、今ではすっかり病気(妄想)の見本市のようになってしまっている棚にも、昔は優れたものがいくつかありました。吉福伸逸さんあたりが監修したのでしょうか、平河出版社の「マインドブックス」は出色でした。ウスペンスキー『奇蹟を求めて』、リリー『意識(サイクロン)の中心』、ダグ・ボイド『ローリング・サンダー』、ハーナー『シャーマンへの道』、ラム・ダス『ビー・ヒア・ナウ』、ハクスレー『永遠の哲学』、イドリース・シャー『スーフィーの物語』等々が砂金のように混じっていたのです。
【ブックガイド】
変性意識状態(ASC)やサイケデリック体験、意識変容や超越的全体性を含めた、より総合的な方法論については、拙著
『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』
および、
『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
をご覧下さい。
ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著
『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』
をご覧ください。