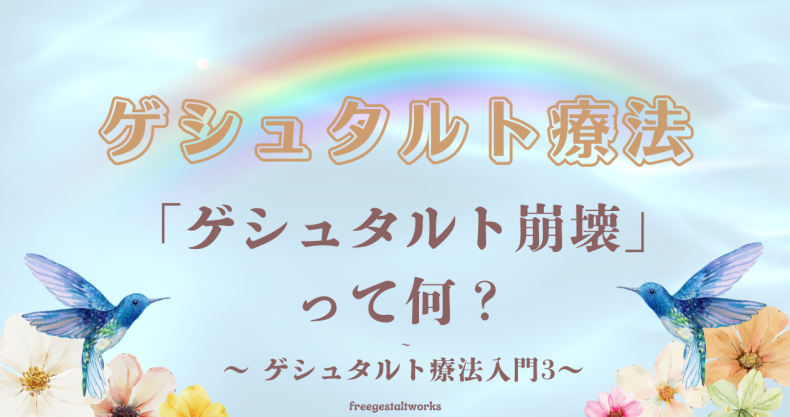- 「この字、こんな形だっけ?こんなんだっけ?」― ゲシュタルト崩壊が起こる瞬間
- ゲシュタルト崩壊とは?
- なぜ、起こるのか?
- よくあるゲシュタルト崩壊の例
- ゲシュタルト崩壊=病気ではない=元に戻す方法
- 言葉のゲシュタルト崩壊もある
- 最後に:人は、いつも“意味”を探している
■「この字、こんな形だっけ?こんなんだっけ?」― ゲシュタルト崩壊が起こる瞬間
「この字、こんな形だったっけ?」
長い時間、同じ文字や漢字を見つめていたり、
何度も書き直していたら、
ある瞬間、それが急に「奇妙な形」に見えて、
「アレ?この字、これで合ってたっけ?」と、
突然、わからなくなってしまったことがないでしょうか?
そして、よく見れば見るほど、ドンドンわからなくなってしまうのです。
これが、「ゲシュタルト崩壊」として知られている現象です。
■ ゲシュタルト崩壊とは?
シリーズの前回記事「ゲシュタルトって何?」では、ゲシュタルト心理学でいう「ゲシュタルトGestalt」について取り上げました。
ゲシュタルト崩壊(Gestaltzerfall)とは、そんな「ゲシュタルトGestalt (全体を意味のあるまとまりとして認識していたもの)」が、瞬時に分解されて(喪失して)、「意味がわからなく」感じられてしまう現象のことです。
たとえば、「後」という漢字を、長い間、じーっと見続けていると、まじまじと見続けていると、「これで合っているっけ?」と混乱するような感覚になります。
これが、「ゲシュタルト崩壊」です。
そして、これは、「認知の仕組み」に由来する心理的な現象なのです。
私たちの認知機能とは、複雑な情報を処理するために、常に「パターン」や「全体像」を下敷きに、それらを先に捉えてから、細部を補完しています。
そのさまざまな「差異」を認知することが重要なわけです。
しかし、同じ文字や形をじっと見続けると、認知機能が、その情報に「慣れ」すぎてしまい、飽和し、「意味」が認識できなくなるのです。
そうすると、漢字が単なる線やパーツの集合体に見えてきて、「何の文字か」が一瞬、わからなくなってしまうのです。
・「後」って、こんな字だったっけ…?
・ロゴマークやアイコンが突然、奇妙な形に見える。
・歌詞カードを読み続けてたら文字が崩れた。
・手書きで「見慣れた漢字」を書いてたら、不安になる。
このような現象に遭遇すると、不安になる人もいるかもしれませんが、これは、誰にでも起こる「認知システムの誤作動」のようなもので、病気ではありません。
むしろ、集中力が高かったり、細部に意識が向いているときほど起こりやすいとも言われます。
そのため、いったん文字や対象から目をそらしたり、少し時間を空けることで、認知機能がリセットされて、また普通に見えるようになります。
「自分がおかしくなってしまったのでは?」と焦らずに、ちょっと休んで、気分転換してみるのが一番です。
実は、ゲシュタルト崩壊は、視覚だけでなく、言葉(音)でも起こります。
同じ単語を何度も声に出して言ってみてください。
例えば「その日、その日、その日、その日、その日、その日、その日……」
だんだん意味がわからなくなってきませんか?
これは「音のゲシュタルト崩壊」と呼ばれることでもあり、同様の現象なのです。
私たちは、常に「意味づけ」や「パターン化」を通して、世界を理解しようとしています。
ゲシュタルト崩壊は、その逆転現象ともいえるものです。
「見えているのに、わからない」
そのような感覚が生まれるとき、私たちは、とても「怖さ」を感じるものです。
実際、ゲシュタルト的な認知は、世界を「意味」としてとらえる、私たちにとっては、とてもかけがえのない機能なのです。
ただ、セラピー的(ゲシュタルト療法的)な見地から見ると、この機能は、私たちにとって、苦痛を生み出すものとして働くこともあるのです。
今後のシリーズでは、そのことを解説していきたいと思います。
【ブックガイド】
変性意識状態(ASC)や意識変容、超越的全体性を含めた、より総合的な方法論については、拙著
『流れる虹のマインドフルネス―変性意識と進化するアウェアネス』
および、
『砂絵Ⅰ 現代的エクスタシィの技法 心理学的手法による意識変容』
をご覧下さい。
ゲシュタルト療法については基礎から実践までをまとめた拙著
『ゲシュタルト療法 自由と創造のための変容技法』
をご覧ください。